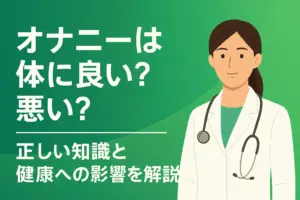40代を過ぎて、以前より些細なことでイライラしたり、家族や職場で感情的に怒ってしまったりすることはありませんか?
「最近どうも調子がおかしい」「自分でもコントロールできないことがある」と感じているなら、それは男性更年期障害のサインかもしれません。
男性更年期障害は、男性ホルモンの一種であるテストステロンの低下などが原因で起こる、比較的新しい概念の病気です。
医学的には「加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)」と呼ばれ、加齢に伴う男性ホルモン(テストステロン)の低下によって引き起こされる症状です(参考:元気プラザ)。
特に「キレやすい」といった精神的な症状は、ご本人だけでなく周囲にも影響を与えるため、どのように対処すれば良いのか悩んでいる方も少なくないでしょう。
しかし、男性更年期障害は症状が現れていても自覚していない男性も多いと言われています(参考:元気プラザ)。
この記事では、男性更年期障害がなぜ起こるのか、特にキレやすさという症状の背景にあるメカニズム、そしてご本人とご家族がそれぞれできる対処法について、専門医監修のもと詳しく解説します。
もし、自分や身近な人に当てはまるかもしれないと感じたら、ぜひ最後まで読んで、適切な対応への一歩を踏み出してください。
男性更年期障害とは?(LOH症候群)
男性更年期障害は、主に40代以降の男性に起こりやすい様々な心身の不調を指します。
医学的には「加齢男性性腺機能低下症(Late-onset Hypogonadism)」と呼ばれ、頭文字をとって「LOH症候群」とも呼ばれます。
特に40代後半から発症し、50~60代に多く見られます(参考:元気プラザ)。
女性の更年期障害が閉経という分かりやすい区切りに伴って起こるのに対し、男性の場合はテストステロンの低下が比較的緩やかに進むため、更年期に気づきにくいことがあります。
また、症状の現れ方や程度にも個人差が大きく、まったく症状を感じない人もいれば、日常生活に支障をきたすほどの重い症状に悩まされる人もいます。
男性更年期障害の主な原因は、男性ホルモンであるテストステロンの分泌量低下です。
テストステロンは、男性の第二次性徴に関わるだけでなく、筋肉や骨の健康維持、性機能、さらには精神状態にも深く関わっています。
このテストステロンが加齢とともに減少することで、様々な不調が現れると考えられています。
テストステロンが低いと、活力と性機能が損なわれ、QOLに大きな影響を与えることとなります(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。
ただし、テストステロンの低下スピードには個人差があり、また加齢以外の要因(ストレス、生活習慣病など)も影響することが分かっています。
なぜ男性更年期でキレやすくなるのか?
男性更年期障害の症状の中でも、特に周囲を困惑させやすいのが「キレやすさ」や「イライラ」といった感情の変化です。
これは、単なる性格の変化ではなく、テストステロンの低下が脳の働きに影響を与えている可能性が指摘されています。
テストステロン低下による精神面への影響
テストステロンは、脳の中でも感情や意欲、認知機能に関わる部位に作用することが知られています。
テストステロンの分泌量が低下すると、これらの脳機能に変化が生じ、精神的な不安定さにつながることが考えられます。
具体的には、以下のようなメカニズムが関与している可能性があります。
- 感情のコントロール能力の低下: テストステロンは、怒りや攻撃性といった感情を調整する脳内の神経伝達物質にも影響を与えている可能性があります。その分泌量が減ることで、感情のブレーキが効きにくくなり、些細なことでも感情的に反応しやすくなることが考えられます。
- セロトニンなど他の神経伝達物質への影響: 精神の安定に関わる神経伝達物質であるセロトニンなどの働きにも、テストステロンが間接的に影響を与えている可能性があります。テストステロンの低下がこれらの物質のバランスを崩し、イライラや不安感を増強させることが考えられます。
- 認知機能の変化: 集中力や判断力の低下も男性更年期障害の症状として挙げられます。これらの機能が衰えることで、物事に対して柔軟に対応できなくなったり、誤解しやすくなったりすることも、イライラや怒りの原因となり得ます。
- 意欲や自信の低下: テストステロンは意欲や活動性にも関わっています。ホルモンが低下すると、何事にもやる気が起きなくなったり、自分に自信が持てなくなったりすることがあります。こうした状態は、周囲の言動に対して否定的に捉えやすくなり、攻撃的な態度につながる可能性があります。
さらに、加齢に伴う仕事や家庭環境の変化、健康問題、将来への不安なども、精神的なストレスとしてテストステロンの低下を加速させたり、既存の症状を悪化させたりする要因となります。
これらの身体的・精神的・環境的な要因が複雑に絡み合うことで、「キレやすい」という症状が顕著に現れると考えられます。
LOH症候群には大うつ病の患者が含まれることが多いとされています(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。
理解すべきは、「キレやすい」状態は、本人の意思や性格だけで引き起こされているわけではないということです。
テストステロン低下という身体的な変化が、感情のコントロールを難しくしている可能性があるのです。
この点を理解することが、ご本人やご家族が適切な対処を行うための第一歩となります。
男性更年期障害の主な症状
男性更年期障害の症状は多岐にわたりますが、大きく「精神症状」と「身体症状」に分けられます。
これらの症状は複合的に現れることが多く、日常生活に様々な影響を与えます。
男性の更年期年齢は40~60歳といわれており、この時期はさまざまな自律神経失調症や神経症状が現れます(参考:元気プラザ)。
症状はEDだけでなく、疲労感、うつ状態、のぼせ、多汗をはじめさまざまです(参考:元気プラza)。
精神症状(イライラ、怒り、不安、抑うつなど)
男性更年期障害の精神症状は、単に気分が落ち込むだけでなく、感情のコントロールが難しくなる点が特徴です。
「キレやすい」という症状は、この精神症状の一つとして捉えられます。
- イライラ・怒りっぽい: 些細なことで腹が立ったり、感情的に怒鳴ってしまったりすることが増えます。以前は気にならなかったことにも過敏に反応し、カッとなりやすくなります。
- 不安感・恐れ: 何か漠然とした不安を感じたり、将来に対してネガティブな考えにとらわれたりすることがあります。理由もなく落ち着かない、そわそわするといった症状も現れます。
- 抑うつ気分・気分の落ち込み: ゆううつな気分が続いたり、何事にも興味を持てなくなったりします。喜びや楽しさを感じにくくなることもあります。
- 集中力・記憶力の低下: 仕事や作業に集中できなくなったり、物忘れがひどくなったりすることがあります。思考力が低下したように感じることもあります。
- 意欲・活動性の低下: 何か新しいことを始めるのが億劫になったり、趣味やレジャーに対する興味を失ったりします。全体的にやる気がなくなり、引きこもりがちになることもあります。
- 自信喪失: 自分に自信が持てなくなり、消極的になります。自己肯定感が低下し、些細な失敗でも深く落ち込むことがあります。
身体症状(疲労感、筋力低下、ED、不眠など)
精神症状と並行して、様々な身体症状も現れます。
これらの身体的な不調が、精神的な負担をさらに増大させることもあります。
- 疲労感・倦怠感: 十分な休息をとっても疲れが取れない、全身がだるいといった症状が続きます。朝起きるのが辛い、午前中から疲れていると感じることがあります。
- 筋力・体力低下: 以前より力が弱くなったと感じたり、階段を上るのが辛くなったりします。運動能力が低下し、すぐに息切れするようになります。
- 関節痛・筋肉痛: 肩こりや腰痛が悪化したり、特に理由もなく関節や筋肉が痛んだりすることがあります。
- ED(勃起障害)・性欲低下: 性欲が以前より明らかに減退したり、勃起しにくくなったり、勃起を維持することが難しくなったりします。これはテストステロンの低下が直接的に関わる代表的な症状です。
- 睡眠障害: なかなか寝付けない、眠りが浅い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど、不眠の症状が現れます。
- 自律神経系の症状: 突然の発汗(ホットフラッシュ)、ほてり、動悸、めまい、耳鳴りなどが現れることがあります(参考:元気プラザ)。
- その他: 頻尿、抜け毛、皮膚の乾燥なども報告されています。
これらの症状は、加齢に伴う自然な変化と区別がつきにくい場合もありますが、複数の症状が同時に現れ、日常生活や社会生活に支障をきたしている場合は、男性更年期障害の可能性を疑ってみる必要があります。
また、LOH症候群は、うつ、性機能低下、認知機能の低下、骨粗鬆症などに寄与するほか、心血管疾患、内臓脂肪の増加、インスリン抵抗性の悪化、HDLの低下、コレステロール値とLDLの上昇にも影響し、メタボリック症候群のリスクファクターになることも指摘されています(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。
さらに、血液中のコレステロール値の増加や、糖尿病、高血圧、動脈硬化、排尿状態にも悪影響を及ぼしていることが最近明らかになってきました(参考:元気プラザ)。
自分でできる男性更年期症状チェック
ご自身の症状が男性更年期障害によるものか判断する手助けとして、簡単なチェックリストがあります。
これは「AMS (Aging Males’ Symptoms) 調査票」と呼ばれるものを参考に、より簡潔にしたものです。
以下の項目について、過去1週間のご自身の状態にもっとも当てはまるものを選択してください。(まったくない:1点、ほとんどない:2点、ときどきある:3点、しばしばある:4点、いつも:5点)
| 症状 | 全くない | ほとんどない | ときどきある | しばしばある | いつも |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 疲労感や倦怠感がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. 関節や筋肉の痛みがある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. 汗をかきやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 眠りが浅い、寝つきが悪い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. 怒りっぽい、イライラしやすい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. 神経質になっている | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. 不安感がある | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. 体力・筋力の低下を感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. ゆううつな気分になる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. ピークを過ぎたように感じる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. 活動性が低下している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. 陰茎の勃起力が低下している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. ひげの伸びが遅くなった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. 性的な能力が低下している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. 朝の勃起がない | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. 性欲が低下している | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. 落胆している、または無気力になってる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計点数を計算してください。
- 26点以下: 症状は軽いと考えられます。生活習慣の改善などで様子を見ましょう。
- 27点~36点: 軽度~中等度の症状がある可能性があります。セルフケアに加えて、気になる場合は専門医に相談を検討しましょう。
- 37点~49点: 中等度の症状がある可能性が高いです。専門医の診断と治療を受けることを強くお勧めします。
- 50点以上: 重度の症状がある可能性が高いです。できるだけ早く専門医を受診してください。
※このチェックリストはあくまで目安です。
正確な診断は医師による診察が必要です。
特に「キレやすい」「イライラ」といった精神症状が強い場合は、点数に関わらず専門医に相談することをお勧めします。
家族が更年期障害でキレやすい場合の対処法
男性更年期障害による「キレやすい」症状は、ご本人だけでなく、一緒に生活する家族にとっても大きな負担となります。
パートナーや家族が突然感情的になったり、怒鳴ったりする状況は、辛く、どう対応していいか分からず悩むことも多いでしょう。
ここでは、家族ができる対処法について解説します。
怒りの背景への理解
まず重要なのは、「キレやすい」という行動が、更年期障害という病気の症状である可能性を理解することです。
これは、本人の性格が急に悪くなったわけではなく、ホルモンバランスの変化や精神的な不調が引き起こしている行動であるかもしれません。
この理解があれば、「自分を責められている」「自分が何か悪いことをしたのか」といった感情に囚われすぎずに済みます。
怒りやイライラは、本人のコントロールが難しい状態からきているのかもしれない、と一歩引いて捉えることが、冷静な対応につながります。
ただし、病気であるからといって、どのような言動も許されるわけではありません。
あくまで「理解」は対応の第一歩であり、その上で適切なコミュニケーションや対応を心がける必要があります。
感情的にならないコミュニケーションの工夫
パートナーや家族が感情的になっているときに、こちらも感情的に反応すると、状況はさらに悪化します。
冷静に対応するためのコミュニケーションの工夫が必要です。
- まずは聞き役に徹する: 相手が怒りや不満を話しているときは、遮らずに最後まで聞く姿勢を見せましょう。共感する言葉(「そうだったんですね」「大変だったね」など)を挟むことで、相手の気持ちが落ち着くことがあります。
- 冷静なトーンで話す: こちらの声のトーンが大きくなったり、早口になったりすると、相手をさらに刺激することがあります。落ち着いた、穏やかな声で話すように心がけましょう。
- 相手の言葉に引きずられない: 相手が攻撃的な言葉を使っても、それを真に受けて反論したり、言い返したりするのは避けましょう。言葉の暴力に対しては、「今の言い方は悲しいな」「そういう言い方をされると聞くのが辛いな」など、自分の気持ちを伝えるにとどめるか、一旦その場を離れることも検討しましょう。
- 「あなた」ではなく「私」を主語にする: 相手を非難するような「あなたはいつも~」「どうして~なの」といった言い方ではなく、「私は~と感じた」「~してくれると嬉しいな」など、「私」を主語にした言い方(アイメッセージ)を意識しましょう。
- 解決策を急がない: 感情が高ぶっているときに、すぐに問題の解決策を見つけようとすると、かえって議論がヒートアップすることがあります。まずは相手の感情を受け止めることを優先し、解決策の話し合いは後日、お互いが落ち着いている時に行う方が効果的です。
適切な距離の取り方
感情的な言動がエスカレートし、身の危険を感じる場合や、自身の精神的な負担が大きすぎる場合は、一時的に距離を取ることも重要です。
- 物理的に距離を取る: 相手が怒鳴ったり、攻撃的な態度をとったりする場合は、一旦その場を離れ、落ち着くまで別の部屋に行くなど、物理的な距離を取りましょう。「少し頭を冷やそう」「一旦落ち着こう」などと冷静に伝えて離れるのが理想ですが、難しい場合は黙って離れても構いません。
- 話す時間を制限する: 感情的な話し合いが長引きそうな場合は、「〇時になったら一度中断しよう」「続きは明日にしよう」などと事前に区切りを決めておくのも有効です。
- 一人になる時間を持つ: 家族をサポートする側も、精神的なエネルギーを消耗します。自分自身の休息のために、一人でリラックスできる時間や、友人などと会って気分転換する時間を意識的に作りましょう。
肯定的な言葉を意識する
更年期障害の男性は、意欲や自信を失っていることがあります。
ネガティブな側面にばかり目を向けるのではなく、良い面に注目し、肯定的な言葉をかけることも大切です。
- 感謝や労いを伝える: 日常の些細なことでも、「ありがとう」「お疲れ様」といった感謝や労いの言葉を伝えましょう。
- 努力や成果を認める: セルフケアに取り組んでいる姿勢や、小さなことでも達成したことに対して、「頑張ってるね」「すごいね」と認め、褒める言葉をかけましょう。
- 存在を肯定する: 性格が変わってしまったように見えても、その人の根幹にある良い部分や、これまでの貢献を忘れずに伝え、「あなたは大切な存在だよ」といった肯定的なメッセージを伝えましょう。
外部のサポートを利用する
家族だけで抱え込まず、外部のサポートを利用することも非常に重要です。
- 信頼できる友人や親族に相談する: 状況を話せる人がいるだけで、気持ちが楽になることがあります。
- 男性更年期障害の専門機関に相談する: ご本人と一緒に受診するのが難しい場合でも、家族が相談に乗ってもらえる医療機関や相談窓口があるか調べてみましょう。
- カウンセリングを受ける: 家族自身の精神的な負担が大きい場合や、対応に悩む場合は、カウンセリングを受けることも有効です。
家族のサポートは非常に大切ですが、ご自身の心身の健康を守ることも忘れてはいけません。
一人で抱え込まず、利用できるサポートは積極的に活用しましょう。
ご本人ができるキレやすさへの自己対処法
更年期障害による「キレやすい」症状に悩んでいるご本人も、自分自身でできる対処法がいくつかあります。
まずは自分の状態を理解し、生活習慣の見直しや感情のコントロール方法を学ぶことから始めましょう。
生活習慣の見直し
健康的な生活習慣は、ホルモンバランスを整え、精神的な安定にもつながります。
更年期症状の緩和に有効とされる生活習慣を見直しましょう。
食事(男性更年期に良い食べ物など)
バランスの取れた食事は基本ですが、特にテストステロンの分泌に関わるとされる栄養素を意識して摂取するのも良いでしょう。
- タンパク質: 筋肉の維持・増強に不可欠であり、テストステロン分泌にも間接的に関わります。肉、魚、卵、大豆製品などをしっかり摂りましょう。
- 亜鉛: テストステロンの合成に重要なミネラルです。牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類などに多く含まれます。
- ビタミンD: テストステロンレベルを上げる可能性が研究で示唆されています。日光浴や、サケ、マグロ、きのこ類から摂取できます。
- バランス: 糖質、脂質も適度に摂り、偏りのない食事を心がけましょう。特に加工食品や糖分の過剰摂取は控えめにしましょう。
男性更年期におすすめの食品例
| 栄養素 | 含まれる食品例 |
|---|---|
| タンパク質 | 鶏むね肉、サケ、豆腐、卵、ヨーグルト |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉(赤身)、豚レバー、アーモンド、カシューナッツ |
| ビタミンD | サケ、マグロ、きのこ類(特にキクラゲ)、卵黄 |
| その他 | ブロッコリー、ほうれん草(抗酸化作用) |
適度な運動(筋力トレーニング、有酸素運動など)
定期的な運動は、テストステロンの分泌を促進し、ストレス解消にも繋がります。
- 筋力トレーニング: スクワットや腕立て伏せなど、大きな筋肉を使うトレーニングはテストステロン分泌を刺激すると言われています。無理のない範囲で、週に2~3回取り入れてみましょう。
- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、水泳などは、全身の血行を良くし、気分転換やストレス解消に効果的です。週に3~5回、30分程度行うのが理想です。
- 継続が大切: 短期間で大きな効果は期待できません。楽しみながら続けられる運動を見つけることが重要です。
質の高い睡眠の確保
睡眠不足はホルモンバランスを崩し、精神的な不安定さを招きます。
質の高い睡眠を十分にとることが大切です。
- 規則正しい睡眠時間: 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるように心がけましょう。
- 快適な睡眠環境: 寝室は暗く、静かで、快適な温度・湿度に保ちましょう。
- 寝る前の工夫: 寝る前にカフェインやアルコールを摂りすぎない、寝る直前のスマートフォンの使用を控える、軽い読書やストレッチでリラックスするなど、自分なりの入眠儀式を作りましょう。
- 昼寝は短時間で: 昼間に眠くなった場合は、20~30分程度の短い昼寝に留めましょう。長い昼寝は夜の睡眠に影響することがあります。
ストレスの適切な解消法
ストレスは更年期症状を悪化させる大きな要因です。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、意識的に実践しましょう。
- 趣味や好きな活動: 自分が楽しいと感じること、没頭できる時間を持つことは、ストレス軽減に繋がります。
- リラクゼーション: 深呼吸、瞑想、ヨガ、アロマテラピーなど、心身をリラックスさせる方法を取り入れましょう。
- 自然との触れ合い: 散歩、ガーデニングなど、自然の中で過ごす時間は心を落ち着かせます。
- デジタルデトックス: スマートフォンやパソコンから離れる時間を作ることも、脳を休ませる上で有効です。
感情のコントロール方法を学ぶ
「キレやすい」自分を変えるためには、感情のコントロール方法を知り、実践することも有効です。
アンガーマネジメントの考え方が参考になります。
- 自分の怒りのパターンを知る: どのような状況で、誰に対して、どのように怒りを感じやすいのか、客観的に分析してみましょう。
- 怒りの衝動をコントロールする: 怒りを感じ始めたら、すぐに行動するのではなく、まずは6秒間待つ、深呼吸をする、その場を離れるなど、衝動を抑える工夫をしましょう。
- 考え方を変える: 怒りの原因となっている出来事に対して、別の見方や解釈ができないか考えてみましょう。「これは自分への攻撃だ」ではなく、「相手は何か困っているのかもしれない」「これは自分にとって学ぶ機会だ」など、ポジティブまたは客観的な視点に切り替える練習をします。
- 言葉を選んで伝える: 感情的に怒鳴るのではなく、「~という行動をされると、私は~という気持ちになります」のように、自分の気持ちを冷静に言葉で伝える練習をしましょう。
すぐに完璧にはできなくても、意識して練習を重ねることで、徐々に感情のコントロールができるようになっていきます。
信頼できる人に相談する
一人で悩みを抱え込まず、信頼できる人に話をすることも、精神的な負担を軽減する上で非常に大切です。
- パートナーや家族: 自分の状態について正直に話し、理解と協力を求めましょう。感情的にならないように、落ち着いているときに話し合いの機会を持つことが大切です。
- 友人や同僚: 近しい関係でなくても、気軽に話せる友人や同僚に愚痴を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
- 専門家: 症状が重い場合や、誰にも話せないと感じる場合は、医療機関やカウンセリング機関の専門家に相談しましょう。
自分の感情や状態を言葉にすることで、客観的に捉えられるようになったり、新たな視点を得られたりすることもあります。
専門医への相談と医療的な対処法
セルフケアを試みても症状が改善しない場合や、症状が重く日常生活に大きな支障が出ている場合は、専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
特に「キレやすい」といった精神症状が強い場合は、一人で悩まず早めに受診しましょう。
病院を受診する目安
以下のような状態であれば、専門医への相談を検討しましょう。
- チェックリストで中等度以上の点数が出た
- 「キレやすい」「イライラ」「抑うつ」などの精神症状が続き、仕事や人間関係に支障が出ている
- 疲労感、EDなど、複数の身体症状が日常生活に影響を与えている
- セルフケア(生活習慣の改善など)を数週間~数ヶ月試しても改善が見られない
- 自分や家族だけで抱え込むのが辛いと感じる
何科を受診すべきか
男性更年期障害の診療は、主に以下の科で行われています。
- 泌尿器科: 男性ホルモンに関する専門知識が豊富で、テストステロン補充療法などを得意としています(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。男性更年期外来を設けている病院もあります。
- 男性更年期外来: 男性更年期障害に特化した専門外来です。泌尿器科医、精神科医、内科医などが連携して診療を行う場合もあります。
- 精神科・心療内科: 精神症状(イライラ、抑うつ、不安など)が特に強い場合や、他の精神疾患の可能性も考慮される場合に適しています。
- 内科: かかりつけ医として、初期相談や他の病気の可能性も考慮してくれます。専門医への紹介が必要か判断してもらえます。
まずは男性更年期外来や泌尿器科を受診するのがスムーズなことが多いですが、精神症状が顕著な場合は精神科・心療内科を検討しても良いでしょう。
事前に病院のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせてみたりして、男性更年期障害の診療を行っているか、どのようなアプローチをしているか確認することをお勧めします。
診断方法(問診、血液検査など)
男性更年期障害の診断は、問診、症状の評価、そして血液検査の結果を総合して行われます。
- 問診: 現在の症状(いつから、どのような症状か、程度はどうか)、既往歴、家族歴、生活習慣(喫煙、飲酒、運動、睡眠、食事)、仕事や家庭でのストレスなどについて詳しく聞き取ります。先述のAMSスコアなどの質問票を使用することもあります。
- 血液検査: 主に血中のテストステロン値を測定します。総テストステロン値や遊離テストステロン値などが測定されます。テストステロン値は日内変動があるため、午前中の空腹時に採血することが推奨されることが多いです。また、他のホルモン(黄体形成ホルモンLH、卵胞刺激ホルモンFSHなど)や、貧血、肝機能、腎機能、脂質、血糖なども同時に調べ、他の病気の可能性を除外したり、全身の状態を把握したりします。
- その他の検査: 必要に応じて、EDの評価(質問票や検査)、骨密度検査、PSA検査(前立腺がんのスクリーニング)などが行われることもあります。
テストステロン値が低ければ即男性更年期障害と診断されるわけではありません。
テストステロン値の低下に加えて、更年期特有の症状が複数見られる場合に診断されます。
主な治療法(ホルモン補充療法、漢方薬など)
診断確定後、症状やテストステロン値、患者さんの希望などを考慮して治療法が選択されます。
- ホルモン補充療法(テストステロン補充療法):
テストステロン値が明らかに低い場合、低下している男性ホルモンを補充する治療です。注射剤、ゲル剤、パッチ剤など、様々な剤形があります。テストステロンを補充することで、意欲向上、疲労感の改善、筋力アップ、性機能の改善、精神症状の緩和などが期待できます(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。- 注射剤: 2週間に1回、または3~4週間に1回程度の頻度で筋肉注射を行います。比較的効果が安定しやすいですが、通院が必要となります。
- ゲル剤: 毎日、皮膚に塗布します。自宅で治療できますが、塗布部位に触れた人へのテストステロン移行に注意が必要です。
- パッチ剤: 毎日、皮膚に貼付します。これも自宅で治療できますが、皮膚刺激やかぶれが起こる可能性があります。
ホルモン補充療法は効果が期待できる一方で、適応を慎重に判断する必要があり、副作用(多血症、睡眠時無呼吸症候群の悪化、前立腺がんの増悪リスクなど)にも注意が必要です。定期的な血液検査などで経過を観察しながら行われます。前立腺がんや重度の睡眠時無呼吸症候群がある場合は、原則としてホルモン補充療法の適応となりません。
- 漢方薬:
テストステロン値がそれほど低くない場合や、ホルモン補充療法に抵抗がある場合などに、症状緩和を目的に用いられます。症状に合わせて様々な種類の漢方薬が処方されます。精神症状(イライラ、不安、抑うつ)に効果があるとされるものや、身体症状(疲労感、ほてり、不眠)に効果があるものなどがあります。
男性更年期障害によく用いられる漢方薬としては、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、加味逍遙散(かみしょうようさん)、桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)などがありますが、体質や症状によって選択される漢方薬は異なります。 - 精神療法・カウンセリング:
精神症状(イライラ、抑うつ、不安など)が強い場合や、ストレスや心理的な要因が症状に大きく関わっていると考えられる場合に有効です。認知行動療法や支持的精神療法などが行われ、感情のコントロール方法やストレス対処法を学ぶことができます。 - ED治療薬:
勃起障害(ED)は男性更年期障害の主要な症状の一つですが、テストステロン補充療法だけでは改善しない場合や、テストステロン値があまり低くない場合のEDに対して、バイアグラ、シアリス、レビトラなどのED治療薬が処方されることがあります。これらは勃起を助ける対症療法であり、男性更年期障害そのものを治療するものではありません。
治療法の選択や効果には個人差があります。
医師とよく相談し、ご自身の症状やライフスタイルに合った治療法を見つけることが大切です。
複数の治療法を組み合わせて行うこともあります。
キレやすさの背景にある他の病気
「キレやすい」「イライラ」といった感情の変化は、男性更年期障害だけでなく、他の病気が原因となっている可能性も考えられます。
自己判断せず、医療機関で正確な診断を受けることが重要です。
うつ病などの精神疾患
更年期障害の精神症状(イライラ、抑うつ、不安など)は、うつ病や適応障害といった精神疾患の症状と似ていることがあります。
LOH症候群には大うつ病の患者が含まれることが多いとされています(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。
- うつ病: ゆううつな気分が強く続き、意欲や関心の低下、不眠、食欲不振などの症状が見られます。男性の場合、典型的な抑うつ症状よりも、イライラや怒りっぽさ、体の痛みといった症状が前面に出やすい「仮面うつ病」として現れることもあります。
- 適応障害: 特定のストレス要因(仕事、人間関係など)が原因で、精神症状や身体症状が現れます。ストレス要因がなくなると症状が改善するのが特徴です。
男性更年期障害とうつ病などが合併していることもあります。
精神症状が強い場合は、精神科や心療内科での専門的な診断が不可欠です。
身体的な疾患の可能性
一部の身体的な病気も、精神症状やイライラを引き起こすことがあります。
- 甲状腺機能亢進症: 甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。動悸、手の震え、体重減少、発汗増加といった身体症状に加えて、イライラや神経過敏、集中力低下などの精神症状が現れることがあります。
- 睡眠時無呼吸症候群: 睡眠中に呼吸が止まったり弱くなったりを繰り返す病気です。睡眠不足により日中の眠気や集中力低下、イライラなどが生じます。
- 脳血管障害: 脳梗塞や脳出血の後遺症として、感情のコントロールが難しくなったり、怒りっぽくなったりすることがあります(脳血管性認知症なども含む)。
- 薬剤の副作用: 一部の薬の副作用として、精神症状が現れることがあります。
これらの病気は、適切な治療によって症状が改善する可能性があります。
男性更年期障害だけでなく、全身の状態を把握するために、医師に症状を詳しく伝え、必要な検査を受けることが大切です。
特に、これまでの健康状態とは明らかに異なる変化が見られる場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
また、男性更年期障害が血液中のコレステロール値の増加や、糖尿病、高血圧、動脈硬化、排尿状態にも悪影響を及ぼしていることも分かっています(参考:元気プラザ)。
まとめ:更年期障害を理解し、適切な対処を
40代以降の男性に現れる「キレやすい」「イライラ」といった感情の変化は、加齢による男性ホルモン(テストステロン)の低下などが原因で起こる男性更年期障害(LOH症候群)の症状である可能性が高いです。
これは単なる性格の変化ではなく、身体的な変化が精神面に影響を与えている状態であり、ご本人にとっても周囲にとっても辛いものです。
男性更年期障害は医学的には「加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)」と呼ばれ、加齢に伴う男性ホルモン(テストステロン)の低下によって引き起こされます(参考:元気プラザ、参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。
特に40代後半から発症し、50~60代に多く見られますが、自覚していない方も多いと言われています(参考:元気プラザ)。
この記事でお伝えしたかった要点:
- 男性更年期障害はテストステロン低下などが原因で起こり、精神症状(キレやすい、イライラ、不安、抑うつ)と身体症状(疲労感、筋力低下、ED、不眠など)が現れます。症状はEDだけでなく、疲労感、うつ状態、のぼせ、多汗をはじめさまざまです(参考:元気プラザ)。テストステロン低下は、うつや性機能低下だけでなく、骨粗鬆症や心血管疾患などのリスクにも寄与します(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。
- 「キレやすい」という症状は、テストステロンが脳の感情コントロールや精神安定に関わる働きに影響を与えることで生じると考えられます。
- ご家族は、怒りの背景に病気がある可能性を理解し、感情的にならないコミュニケーションを心がけ、時には適切な距離を取り、ご自身の心身も守ることが大切です。肯定的な言葉かけも有効です。
- ご本人は、生活習慣の見直し(バランスの良い食事、適度な運動、質の高い睡眠、ストレス解消)や、感情のコントロール方法を学ぶことで症状の緩和を目指せます。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することも重要です。
- 症状が重い場合やセルフケアで改善しない場合は、泌尿器科や男性更年期外来などの専門医に相談しましょう(参考:順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科)。問診や血液検査で診断し、ホルモン補充療法、漢方薬、精神療法などで治療を行います。
- 「キレやすさ」の背景には、うつ病などの精神疾患(LOH症候群には大うつ病の患者が含まれることが多い)や、甲状腺疾患、睡眠時無呼吸症候群などの身体的な病気が隠れている可能性もあります。また、コレステロール値増加や糖尿病など生活習慣病との関連も指摘されています(参考:元気プラザ)。自己判断せず、医療機関での正確な診断が不可欠です。
男性更年期障害は、適切な理解と対処、そして必要に応じた医療的なサポートによって、症状の改善が見込める状態です。
ご本人もご家族も、諦めずにまずは一歩を踏み出すことが大切です。
ご自身の状態を把握し、できることから生活習慣を見直し、必要であれば迷わず専門医に相談してください。
更年期を乗り越え、心穏やかに過ごせるよう、適切な対処法を見つけましょう。
免責事項:
この記事は情報提供を目的としており、特定の治療法や医療機関を推奨するものではありません。
読者の皆様の健康状態や症状は個々に異なります。
診断や治療については、必ず医療機関を受診し、医師の判断に従ってください。
本記事の情報に基づいた行動によって生じたいかなる結果についても、当方は一切の責任を負いかねます。